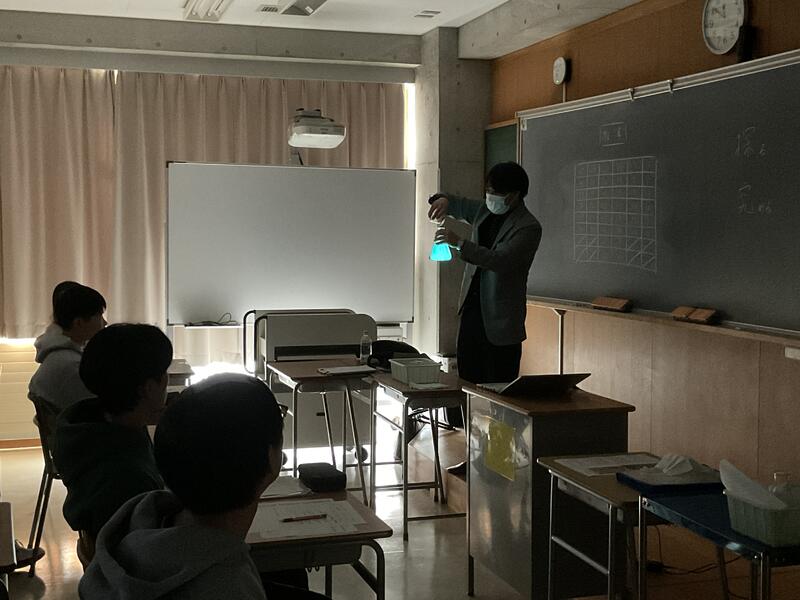|
令和7年度の取り組み 令和7年度SSH中間報告会・授業づくりプロジェクトフォーラム 令和7年12月17日(水)に令和7年度SSH中間報告会・授業づくりプロジェクトフォーラムを開催いたしました。県内外より79名の方々にご参加をいただきました。 午前の研究授業Ⅰでは本校教員による16クラスの授業を公開させていただきました。今年度も「三高型STEAM教育」「尚志ヶ丘フィールドの活用」「リーディングDXスクール事業」の3つのテーマを主軸として、「探究的な学び」の実現を目指したこれまでの研究成果を参観いただきました。 研究授業Ⅱでは和歌山県立向陽高等学校の谷地祐介先生、山本玄先生に本校の学校設定科目である「SSサイエンス総合」の授業を実践していただきました。サイエンスと古典の教科横断型の授業を構成していただき、『うつほ物語』「俊蔭」を題材として、教科の枠をこえた視点の重要性について示唆していただきました。あらゆる授業の場面で科学的な視点を持つことの重要性が示され、課題研究のテーマ設定における資質・能力の育成につながる授業となりました。また西武学園文理高等学校の笠原諭先生には「現代の国語」の授業を実践していただきました。デジタルシチズンシップの考えにもとづいて、生成AIによるハルシネーションにどのように対応していくか、科学的な根拠を示しつつ、批判的思考力をどのように育成するべきかを示していただきました。また生成AIの活用のみならず、授業におけるICT活用についても多くの学びがありました。 さらに2年生理数科のResearch Expression Ⅱでは、課題研究についての英語によるスライド相互発表、2年生普通科ではイノベーション探究Ⅰにおけるポスター発表をiPadで実施しました。 午後の基調講演では早稲田大学教職大学院教授 田中 博之氏より「生成AIを活用した探究的な学習の在り方」を演題としてご講演をいただきました。生成AIの活用にはまだまだ不安な点が多い中で、積極的な活用を実施していくために具体的な事例を踏まえて探究的な学びにつなげていく手法をご紹介いただきました。生成AIを活用した探究学習の在り方についての高等学校の事例、生成AIの特徴やプロンプト、AIリテラシー教育の重要性や、主体性・協働性・創造性を育む探究的学習との融合により、課題設定、情報検索、発信を支援し、深い思考や課題解決能力の育成につながる可能性を示していただきました。 基調講演後は7つのグループに分かれて研究協議を行いました。今年度はあらかじめ参観者の皆様から研究協議のテーマを募集し、そのテーマに沿って授業方法や探究的な学びについてグループワーク等で意見交流を実施しました。 限られた時間ではありましたが、皆様のご協力のもとで大変実りある研究会を実施することができました。あらためて御礼申し上げます。 第2回校内研修 令和7年9月11日(木)に、SSH事業の制度に関する今後の見直しや、次期学習指導要領に向けた中央教育審議会の内容を踏まえ、これからの学校運営の方向性を全職員で共有すること。また具体的な事業についてグループワークで意見交流を行いながら、事業改善につなげていくことを目的として第2回校内研修を実施しました。 はじめに理数科部長の村田淳先生より、SSH事業の制度見直しについて説明いただきました。これまでのSSH事業の成果をさらに発展させる目的で、目指す人材育成内容や規模に応じて、支援のあり方を変えていくことや、本校におけるSSH事業の方向性について国際共同研究や、産学官連携等の取組を発展させることについて述べられました。つづいてSSH-授業づくり研究センター長の渡部敦先生より、現在審議されている次期学習指導要領の方向性について説明いただきました。まず現行学習指導要領の現状と課題、それを踏まえた改訂のポイントについて、「柔軟な教育課程の編成」、「探究的な学びの一層の充実」、「デジタル化と個に応じた指導」などにわけて、説明されました。 説明ののち、学校の事業に関する改善点をグループごとに意見交流を行い、その内容をFigmaに集約しました。学校設定科目のアイデアや働き方改革の進め方など、さまざまな意見を教職員全体で共有することができ、今後の事業改善につながる研修となりました。
第1回校内研修 令和7年6月12日(木)に、生徒の学習状況や段階などを踏まえた授業実践やカリキュラム開発、教材開発などのプロセスに関する事例から、持続可能な社会の実現に向けた資質・能力を育成するための手法を学ぶことを目的として第1回校内研修を実施しました。 講師に、昨年度まで、神戸大学附属中等教育学校で教鞭をとられており、今年度より大阪公立大学国際基幹教育機構教職センターでご活躍なさっている森田育志氏をお迎えし、「持続可能な社会の創り手を育むESDの授業開発ー共創および探究を手がかりとしてー」を演題としてご講演いただきました。 はじめにESDについて、学校教育の中核に位置付けられ、カリキュラム全体に及ぶ重要な教育概念であることを述べられ、自身が前任校で実践していた学校設定科目「ESD」の開発や実践内容を実際の授業動画も踏まえて説明していただきました。授業で実践した問いを参加者に問いかけ、グループワークなどで参加者が一緒に考えていくことで、新しい視点を与えていただきました。森田氏の授業実践では学習内容を生徒が主体的に考えるという手法なども活用され、このような学習者主体の授業づくりの考えなどから、今後の授業改善へ向けた重要な示唆を与えていただきました。
令和6年度の取り組み 令和6年度SSH中間報告会・授業づくりプロジェクトフォーラム 令和6年12月18日(水)に令和6年度SSH中間報告会・授業づくりプロジェクトフォーラムを開催いたしました。県内外より118名の方々にご参加をいただきました。 午前の研究授業Ⅰでは本校教員による16クラスの授業を公開させていただきました。今年度は「三高型STEAM教育」「尚志ヶ丘フィールドの活用」「リーディングDXスクール事業」の3つのテーマを主軸として、「探究的な学び」の実現を目指したこれまでの研究成果を参観いただきました。 研究授業Ⅱではドルトン東京学園中等部・高等部の沖奈保子先生に「言語文化」の授業を実践していただきました。「虫めづる姫君」の人物像を読み取り、現代と同様の考えや価値観を持つ人物や出来事を新聞から探すことで、古典で得られた情報をどのように活用するか、授業を通じて生徒の学びを深めていただきました。また神奈川県立生田東高等学校の秋山紀将先生には「SS理数データサイエンス」の授業を実践していただき,確率論の誕生とも言われる、パスカルとフェルマーの文通のやり取りで扱われた問いを利用し、パスカル役であるChatGPTを納得させる活動を通じて、生成AIの利活用とともに、論理性のある説明をどのように構築するかをご指導いただきました。 さらに2年生理数科のResearch Expression Ⅱでは,課題研究についての英語によるスライド相互発表,2年生普通科ではイノベーション探究Ⅰにおけるポスター発表を実施しました。 午後の基調講演では京都大学大学院教育学研究科教授 西岡 加名恵氏より「高等学校における「探究的な学習」の評価-パフォーマンス評価をどう活かすか-」を演題としてご講演をいただきました。育成するべき資質能力を踏まえ、各教科における学習評価についてパフォーマンス課題とその評価について具体的に説明していただきました。さらに探究的な学習がどのようにすすめられるべきか、各教科で培われる「見方・考え方」を含めたカリキュラム全体のあり方や具体的な評価法について、多様な実践例とともにご紹介いただきました。 基調講演後は7つのグループに分かれて研究協議を行い,授業方法や探究的な学びについて活発な意見交流を実施しました。 限られた時間ではありましたが,皆様のご協力のもとで大変実りある研究会を実施することができました。あらためて御礼申し上げます。
第2回校内研修 令和6年9月5日(木)に今年度第2回目の校内研修を実施しました。探究活動の具体的な指導について、どのように生徒と伴走していくかをテーマとしてグループワークを実施しました。 本校で海洋プラスチックの探究活動を指導している南部拓未先生、尚志ヶ丘フィールドの「時習の森」を題材とした探究活動を指導している佐々木敦先生より実践事例を紹介していただきました。生徒が探究したいテーマを尊重しながら、研究意義や研究自体の面白さに気付かせる、巧みな指導法を、実際の場面を交えて説明していただきました。 その後中野剛先生によるFigjamの利活用についての説明を受けながら、Figjamを活用したグループワークを実施しました。実際の2年生普通科のポスターを使用して、テーマに関連する要素を抽出し、新しい探究の視点を示せるテーマを班ごとに作成しました。Figjamの操作方法を学びつつ、探究の指導に関する新しい視点を得ることができ、今後の探究指導や授業改善に活かせる内容となりました。 第1回校内研修 令和6年6月6日(木)に今年度第1回目の校内研修を実施しました。生徒の探究活動がより自律的に実施され、社会参画を目指したものになることや、課題解決法の整合性やテーマの鋭角性、広角性が高められる指導法のヒントを学び、今後の探究活動や授業改善に活かしていくことを目的として、東北芸術工科大学 高大連携推進部長・デザイン工学部 教授 柚木 泰彦 氏からご講演をいただきました。 デザイン思考を活用した探究学習の進め方について、実際に「仙台三⾼⽣が探究活動を進めやすい環境づくりのために教員ができること」をテーマにグループワークに取り組みながら、探究学習の手法を学びました。講演を通じて、普段感じていた指導上の課題についての本質を見出し、具体的な解決策のアイデアをまとめました。実際の探究活動の思考を体験できたことで、これからの生徒の探究活動に際しても有意義なアドバイスができると実感しました。 |
|
令和5年度の取り組み 令和5年度SSH中間報告会・授業づくりプロジェクトフォーラム 令和5年12月19日(火)に令和5年度SSH中間報告会・授業づくりプロジェクトフォーラムを開催いたしました。県内外より96名の方々にご参加をいただきました。 午前の研究授業Ⅰでは本校教員による16クラスの授業を公開させていただきました。今年度は「三高型STEAM教育」「尚志ヶ丘フィールドの活用」「リーディングDXスクール事業」の3つのテーマを主軸として取り組んだ研究成果を見ていただきました。 研究授業Ⅱでは神戸大学附属中等教育学校の森田育志先生に「公共」の授業を実践していただきました。ESDの観点から科学技術がもたらす豊かさについて、対話を中心とした深い学びの場をどのように構築していくかについて、ご指導いただきました。また大阪教育大学附属高等学校池田校舎の森田琢也先生には「Research Expression Ⅰ」の授業を実践していただき,CLILの手法を用いて、芸術と商業的価値について考察し、価値は何によって決定付けられるかを考えていく授業が展開されました。英語によって思考力を高めていく方法について、ご指導いただきました。 さらに2年生理数科のResearch Expression Ⅱでは,課題研究についての英語によるスライド相互発表,2年生普通科ではイノベーション探究Ⅰにおけるポスター発表を実施しました。 午後の基調講演では一般社団法人こたえのない学校理事長 藤原 さと氏より「協働する探究のデザイン社会をよくするプロジェクトデザインとは?」をテーマとしてご講演をいただきました。探究学習の重要性が叫ばれている中で、探究学習に関する歴史的な系譜や「学び」のレベルを構造的に示しながら、探究学習の意味付けを丁寧に説明していただきました。またご自身のプログラムや実践例をご紹介いただきながら、探究学習の方向性を我々に示していただきました。 基調講演後は7つのグループに分かれて研究協議を行い,授業方法や探究的な学びについて活発な意見交流を実施しました。 限られた時間ではありましたが,皆様のご協力のもとで大変実りある研究会を実施することができました。改めて御礼申し上げます。 第2回校内研修 令和5年9月7日(木)に今年度第2回目の校内研修を実施しました。探究的な学びをどのように構築していくかをテーマとして、本校で「SSデータサイエンス」を担当している板橋淳先生、「日本史探究」で教科横断的な学びやデータ活用による探究的な学びを実践している佐藤和道先生より、実践事例を紹介していただきました。その後,教科ごとのグループで探究的な学びを実践するために,学びの設計図を作成しました。最後に、作成した学びの設計図を各班から発表してもらい、さまざまなアイディアを全職員で共有しました。今後の授業にいかせる有意義な研修となりました。
第1回校内研修 令和5年7月3日(月)に今年度第1回目の校内研修を実施しました。現行の学習指導要領に対応した授業改善や身に付けさせたい資質・能力を具体的に知るため,大学入試センター試験問題調査官の穗積曉氏からご講演をいただきました。 学習指導要領で示された内容を適切に評価するために大学入学共通テストが作成され、教科の見方、考え方等を踏まえた「主体的・対話的で深い学び」の重要性を説明していただきました。また資料やデータにもとづいて、考察したり、分析するなど探究的な学びや協働的に課題に取り組んだりする場面を想定しており、本校で実践している教科横断的な学びやPBLの学習方法が効果的であることも再確認できました。講演内容を受け、授業改善へ向けた取組をさらに進めていきたいと思います。 |
学校づくりプロジェクト
平成30年度に,これまでのプロジェクトの集大成として「建学の精神」に基づく「学校教育目標」の改編を全職員で行いました。そして令和元年度に「学校教育目標」を実現するための「生徒に育成する6個の資質・能力」を全職員で作成しました。どの教育活動でどの「資質・能力」を育成するかを各学年・分掌部が検討,決定し,さらに生徒が各行事等を振り返ってどの程度「資質・能力」が身についたかを自己評価するためのルーブリックも作成しました。生徒は前期・後期の年2回自己評価をします。その結果をもとに各行事等が仮説通りに生徒の「資質・能力」を育成できているかどうかを各学年・分掌部が検証していきます。
1 学校教育目標
①仙台三高は,多様な人々と協働する寛容な心を持ち,社会の変化にしなやかに対応する,逞しく豊かな人間性を育みます。
②仙台三高は,人類が積み上げた英知に学び,真理の追求を通して知性と感性を磨き,事象を深く探究する態度を養います。
③仙台三高は,博愛の精神と創造する知を育む人づくりを通して,よりよき未来の創出に貢献します。
2 育成したい6つの資質・能力
①自己管理力
心身の健康を維持するために、健全な生活習慣を身につけ、様々な壁を柔軟に乗り越えるしなやかさを持つ。
②信頼構築力
相手の立場を思いやり、尊重し、互いに信頼関係を築くことができる。
③自己研鑽力
人類が築き上げてきた真理を重んじ、それを教養として身につけることを通して、自らの資質・能力を高めようとする。
④課題突破力
困難な課題に立ち向かい、解決するために、個人の資質を高め、チーム一丸となる実行力を持つ。
⑤未来デザイン力
未知なるものに立ち向かうために、自己の可能性や周囲の可能性を信じ、能動的に知性を高め行動していく。
⑥社会牽引力
他者理解力・思考力など総合的な判断力をもって、集団を牽引し、社会貢献し、共生して生きていく。
(参考)
H30.9 校内研修:「三高生に身につけさせたい資質・能力」を「建学の精神」をもとに全職員で30個にまとめる。
H31.3 校内研修:9月にまとめた30個の「資質・能力」をもとに全職員で3つの「学校教育目標」を改定する。
R1.9 校内研修:H31にまとめた30個の「資質・能力」を全職員で6個にしぼる。
R2~ 6個の「資質・能力」をどの教育活動で身につけるか検討し,その成果を測る。
『SSH-授業づくり研究センターとは』
平成27年度に設置されたSSH-授業づくり研究センターは,平成22年度にスタートした本校独自の授業研究・改善,教員研修の取り組みである授業づくりプロジェクトを進展させること,また,同じく平成29年度に再指定を受けたSSHおよびその指定のない期間の中継事業であるグローカル・サイエンスとの連携を強化することを目的としています。
全職員がSSH事業部と授業づくり事業部に所属し,事業・プロジェクトごとにリーダーを配置し,それぞれ研究や開発,企画・実践を行っています。
組織・事業図
『研究センターについて』
SSH-授業づくり研究センター設立の目的(H27)
①SSH,授業づくりプロジェクト双方にまたがる分野での,協働・共有の推進と調整
②授業づくりプロジェクト本体の運営主体
所属は全職員
『事業部について』
SSH事業部
・目標と事業内容
SSH事業の運営,課題研究を中心とした授業法・評価法の研究,21世紀型能力育成の研究・開発。
授業づくり事業部
・目標と事業内容
授業法・評価法の研究とその実践としての教育プログラム開発及び,高大接続改革・高校教育改革対応,21世紀型能力育成の研究・開発。
『授業づくりプロジェクト立ち上げからその後の経過』
H22.12 仙台三高ならではの新たな研修システム構築の理念を校長より提示
「三高スタイルの授業開発」「生徒の変容を把握する評価法の開発」を
目的にプロジェクト立ち上げ(それらの開発を通じての校内教員研修)
H23. 4 ワークショップⅠ・Ⅱにより,授業の三観点 「生徒主体」,
「知的好奇心」「考える」を設定
H27. 3 SSH-授業づくり研究センター設置
H28. 4 GS-授業づくり研究センターへ改称 全職員所属
H29. 4 SSH指定(2期目),SSH-授業づくり研究センターへ改称
宮城県仙台第三高等学校
〒983-0824
仙台市宮城野区鶴ケ谷1丁目19番
TEL : 022-251-1246
FAX : 022-251-1247
本校生徒会メンバーによるInstagramを開設しています。
皆さんに仙台三高の魅力が伝わるような内容発信をしています。
トピックスがありません。
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。