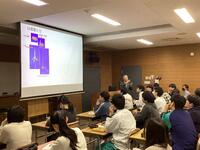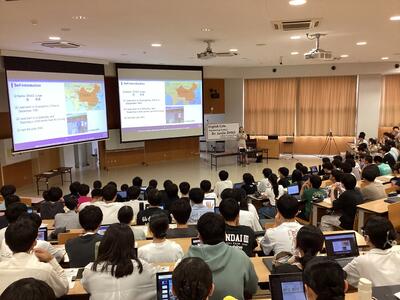カテゴリ:授業の様子
【12/4】SSHコーディネーター講演「課題の設定の仕方」 ~第一線の研究者から学ぶ,研究の核心~
令和7年12月4日(木)、本校1年生理数科80名を対象にSSHコーディネーターによる講演「課題の設定の仕方」が行われました。
この講演は今後生徒たちが取り組む課題研究に向けて、研究テーマを設定する際の考え方や重要な視点を学ぶことを目的としています。
第一線で活躍する研究者の経験に基づく話は、生徒たちにとって大きな刺激となりました。
講演の冒頭では、SSHコーディネーターが自身の研究テーマである「エチレンの作用機作」や「水生植物の適応生理」を例に挙げながら、学術研究における課題設定のプロセスを解説しました。
「何を明らかにしたいのかを明確にすることが、研究の出発点である」という言葉に、生徒たちは深くうなずいていました。続いて、学術研究の課題設定に必要な要素として、次の3点が示されました。
・未解決の課題への挑戦(独創性)
・検証する手段(施設・技術)
・新たな理論や概念の発表(評価)
これらを踏まえ、「課題は単なるテーマ決めではなく、科学的な問いを立てること」であると強調されました。
また、情報収集と整理の重要性にも触れ、「ネーチャーやサイエンスに載っている論文であっても、鵜呑みにせず疑う姿勢が大切」という言葉が印象的でした。研究活動の本質について「課題設定はゴールではなく、探究の始まり。問いを持ち続けることが科学の醍醐味」と語られ、生徒たちは真剣な表情でメモを取りながら耳を傾けていました。
また、生徒たちはGoogle Scholarなどを活用した先行研究の調べ方や生成AIの活用についてもアドバイスを受けました。
講演後、生徒からは次のような感想が寄せられました。
「今回の講演会から研究テーマ決定に重要な要素は2つあると考えました。1つ目は疑問点をもつということです。研究の中で様々なことに疑問をもつことで最終的な研究テーマへつながっていることを知りました。また、2つ目は情報収集です。いざ調べてみると、自分が研究しているものと同じものがあることがあるので、しっかり調べて知識を吸収したいです。」
今回の学びは、今後の課題研究において、科学的な視点と主体的な姿勢を育む大きな一歩となるでしょう。
【10/7】生物 ✕ 倫理
先日、3年生「理数生物、生物」の授業において、倫理科と連携した教科横断型STEAM授業(生物 ✕ 倫理)を行いました。
今回のテーマは「利他行動(自己の利益を犠牲にして他個体を助ける行動)」です。
授業では、まず倫理の視点から「人間における利他行動」を、次に生物の視点から「動物における利他行動」を考察しました。
その後、両者を比較することで共通点や相違点を探究し、多角的な視点から「利他行動」の本質に迫りました。
生徒たちは、理系・文系の枠を超えた視点で学ぶこの授業を楽しみにしてくれていたようです。授業後も活発に議論を交わしたり、テーマについて深く思考を巡らせたりする姿が見られ、知的な刺激にあふれた時間となりました。
【10/22】生物基礎 時習の森調査
仙台第三高校の1学年「生物基礎」では、「生物の多様性と生態系」の学習の一環として、学校林「時習の森」で実習を行いました。
実習では、先輩たちが設置してくれた樹木札を手がかりに、森林がどのような階層構造(高さによる光環境の違いなど)になっているかを自分たちの目で観察しました。
また、樹木が倒れるなどして林冠(森の天井部分)が途切れた「ギャップ」を探し、そこでの植生の様子も確認しました。
教室で学んだ知識を、実際のフィールドで確認することは、生徒たちにとって学びを深める貴重な体験となったようです。生徒たちはグループで互いに協力しながら、熱心に森の調査に取り組んでいました。
【10/15】ライフサイエンスの授業で「VR介護体験」を実施しました。
令和7年10月15日(水)の2・3校時、本校1年生理数科80名を対象に、宮城県保健福祉部主催の介護体験出前授業を実施しました。株式会社シルバーウッドの黒田様を講師にお招きし、最新のVR技術を使った認知症体験を通じて、介護への理解を深める貴重な機会となりました。
生徒全員がVRゴーグルを着用し、「レビー小体型認知症」の方が見る世界をバーチャルリアリティで体験しました。突然視界に現れる幻視(幻覚)や、距離感が掴みにくいなどの症状を疑似体験することで、当事者にとってどのような「困りごと」になっているのかを、深く、リアルに理解することができました。
このVR体験を通じて、生徒たちは「介護する側」の視点だけでなく、「介護される側」の視点を初めて持ち、相手の立場に立って考えることの重要性や介護する際の心構えを学びました。
【9/17】生物基礎 ✕ 免疫劇場
仙台第三高校の生物基礎の授業では、「生体防御」について学んでいます。免疫に関わるさまざまな細胞の特徴や、それらがどのように連携して細菌やウイルスから体を守っているのかを理解するために、生徒たちはこの仕組みを擬人化した劇で表現しました。
各班はストーリーを丁寧に練り上げ、自分たちで小道具を準備し、協力しながら演技を通して学びを深めました。細胞たちが登場人物として活躍する劇を通じて、生徒たちは楽しみながら免疫のしくみを体感的に理解することができました。
【7/15 (火)】SS English Café を実施しました!
令和7年7月15日(火)に、本校にて『SANKO ENGLISH CAFÉ』が実施されました。大学の研究者をお招きし、3学年全生徒対象に、以下のような研究分野に関する講義を実施いただきました。
【理系生徒対象】『キラル選択性ガラスセラミクスの物質開拓と設計指針の確立』:Junjie ZHAO先生(東北大学)
【文系生徒対象】『気候正義(Climate Justice)と地球環境保全のためにできること』Giselle L. MIOLE先生(東京大学)
講義では、研究そのものに加え、講師の先生の出身国やその文化、研究者を志した理由を始めとした内容まで扱って頂きました。大学の学びに対するイメージを具体的に持つことができただけではなく、1つの学びを深く追究していくことのおもしろさややりがいを学ぶことができました。また、文系生徒対象の講義では、生成AIにプログラムされたクイズに各自挑戦するなどのアクティビティも行われ、自らの選択が環境・経済・文化にどのような影響を与えるのかを実践的に学ぶことができ、主体的に講義へ参加することができました。
授業後に実施したアンケートでは、講義全体に対する反響が多く寄せられました。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 生徒の感想 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
「外国人の先生だと、日本と違う環境で国や気候変動を見てきたことから、新しい視点で気候変動、地球温暖化について考えることが出来、とても良い時間だったと思う。」
「異文化を背景に持った研究者と関わることができて良い経験になった。」
「リスニングの力や要約する力を養えるだけではなく、英語での研究のプレゼンの仕方や海外の人の研究で重視する所や研究を組み立てる上でのプロセスなど日本人にはない視点を学ぶことができた。」
「内容は難しかったが、比較的易しい表現を選んでくれていたのでとても理解しやすかった。逐一図と解説が入っていたのでそこもわかりやすかった。」
1年生 生物基礎「生物の多様性と生態系」「時習の森」授業紹介
仙台第三高校1年生の生物基礎の授業では、学校林「時習の森」を活用した特色ある授業を展開しています。
今回は、「生物の多様性と生態系」の単元の一環として、森の各地点の土壌中に生息する生物の種類を、ツルグレン装置を用いて調査しました。
時習の森の土壌生物の多様性については、これまで詳細な調査が行われておらず、未知の領域です。 生徒たちは、自分たちで採取したデータをもとに、森の状態を考察するという貴重な経験をしました。
学年全体でデータを集計し、様々な角度から分析することで、森の生態系についてより深く理解することができました。
今回の授業を通して、生徒たちは生物多様性の重要性や、自然環境を守ることの大切さを改めて認識しました。
1年生 生物基礎「時習の森」の観察
1年生生物基礎の授業では、森林の階層構造や、森林にできるギャップについて学習しました。
仙台三高の隣の森では実際にその様子が見られるため、観察を行いました。
以前、他の授業でも森の観察は行いましたが、学習した知識があると見える景色も違って見えます。
どのような場所で階層構造が見られるか、どこにギャップがあり林床の様子はどのようになっているか、など生徒は森に散らばって学んだことが理解できる場所を時間内に探し回りました。
「生物✕倫理」利他行動について
3年生の生物の授業では、倫理の先生とコラボし、生物の利他行動について考える授業を行いました。
生物の利他行動についての例を、倫理の先生、生物の先生それぞれから学び、両者の共通点や相違点について考えました。
今回はFigjamを使い、お互いに意見を交わしながら考えをまとめました。
コラボ授業「生物×倫理」
3年生理数生物の授業では、倫理の先生とコラボし、利他行動の意味について考える授業を行いました [生物 ✕ 倫理]
ハチの例などから生物的な方向から考える場合と、小説「小僧の神様」を読み倫理的な方向から考える場合を合わせ、自分なりに考える利他行動の意義をまとめました。
相手の考えが自身と異なるところも多く、様々な面から利他行動を考える学びの多い授業になりました